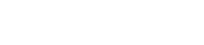Education
専門研修・教育について
兵庫県の基幹病院として循環器疾患全般の高度医療を行っています。虚血性心疾患・不整脈・弁膜症・大動脈疾患・下肢末梢動脈疾患などのそれぞれ専門性を確立した診療チームを構成し、集中治療や緊急カテーテル、緊急手術を要する症例に対して24時間365日対応しています。
治療実績
Achievement
当院では多領域での豊富な症例数とともに経験豊富な指導医による教育体制を整えております。最高水準の技術を学べる環境、充実した研修プログラムを提供しています。
治療実績はこちらをご覧ください。
認定施設
Certified Facilities
循環器に関する多数の認定施設であり、豊富な症例と充実した指導医体制によって次世代の優れた循環器専門医師を養成することにも注力しています。
- 日本内科学会専門医研修プログラム
- 日本循環器学会認定循環器専門医研修施設
- 日本循環器学会左心耳閉鎖システム実施施設
- 日本不整脈心電学会認定不整脈専門医研修施設
- 日本不整脈心電学会経皮的カテーテル心筋冷凍焼灼術[クライオバルーン]実施施設
- 日本不整脈心電学会パワードシースによる経静脈的リード抜去術施設基準
- 日本不整脈心電学会経皮的カテーテル心筋冷凍焼灼術 [レーザーバルーン]実施施設
- 日本不整脈心電学会経皮的カテーテル心筋冷凍焼灼術 [POLARx 冷凍アブレーションカテーテル]
- 日本不整脈心電学会パルスフィールドアブレーション[VARIPULSE]施設基準
- IMPELLA補助循環用ポンプカテーテル実施施設
- 日本超音波医学会専門医研修施設
- 日本ステントグラフト実施基準管理委員会胸部・腹部ステントグラフト実施施設
- 日本心血管インターベンション治療学会認定研修施設
- 浅大腿動脈ステントグラフト実施基準管理委員会浅大腿動脈ステントグラフト実施基準による血管内治療の実施施設
- 日本心臓血管内視鏡学会認定教育施設
当直・オンコール体制
Duty/on-call system
専門研修での割当の目安は以下のとおりとなります。
当直:3日/月
オンコール(緊急カテーテル待機):8日/月
※事前申請で日程を調整することが可能です。
研究活動
Research Activities
臨床研究にも積極的に取り組み、学会活動や論文作成など国内外に情報発信を行っております。
多施設臨床研究を含めて様々なテーマに取り組んでおり、専門研修期間中でもデータベースの取り扱い・解析、学会発表の校正、論文化まで一貫して学ぶことができます。
学術論文実績はこちらをご覧ください。
各部門からのメッセージ
Messages
虚血性心疾患グループ

年間200件程度の急性冠症候群に対するPCI治療を行っており、早い時期から急性冠症候群に対する治療・集中管理を経験できます。慢性冠症候群に関しては、アテレクトミーデバイスが必要な高度石灰化病変、慢性完全閉塞性病変といった複雑病変に対するPCIも行っております。最新のデバイスも積極的に取り入れ、虚血性心疾患の最先端の治療を提供しています。専攻医の先生方には、まずはカテーテル検査の自立、PCI副術者として知識・技術の習得を目標に多くの症例を経験いただきます。その後、経験に合わせてシンプルな病変から指導医の下でPCI治療を行っていただきます。
不整脈グループ

カテーテルアブレーションの実施件数は年間700件と多く、一人当たりの手術件数も200-300件と多いのが特徴です。また心房細動だけでなく、上室性頻拍症や心室性不整脈のアブレーションやペースメーカ植込み、カテーテル左心耳閉鎖術などの不整脈全般の治療手技を豊富に経験できます。加えてそれを支える教育体制、優秀なコメディカルにも恵まれており、不整脈医として大きく成長することができます。ご希望の先生には臨床研究にも取り組んでいただき、学会発表はもちろん論文執筆までサポートします。
構造的心疾患、大動脈疾患グループ

心臓カテーテル治療と言えば冠動脈インターベンションでしたが、弁膜症治療を代表とする ”structural heart disease (SHD、構造的心疾患) インターベンション” が近年注目されています。この分野においては、経カテーテル大動脈弁留置術(TAVR)による大動脈弁狭窄症治療の進歩が目覚ましく、当院でも積極的に取り組んでいます。更に、循環器内科では経験できる施設が少ない大動脈ステントグラフト治療も多数経験することでき、専門研修期間中に実施医を取得し指導医に必要な症例を経験することが可能です。
下肢末梢動脈疾患グループ

専門研修1年目は穿刺・止血から開始し、カテーテル治療を学んでいただきます。病棟管理も主体的に取り組んでいただきますが、必ず常勤スタッフとペアで患者さんを担当しますので、治療方針をいつでも相談できます。専門研修3年目で狭窄病変はもちろん、短い閉塞病変までオペレーターとして完遂できることを目標に指導を行っております。