2019.02.18
前回は「日本に多い胃がん」についてご紹介しました。内容はこちら
進歩する内視鏡診断 -NBIと拡大内視鏡ー
現在の技術では、上部消化管内視鏡は高画質な電子画像での撮像ができ、わずかな陥凹や色調の違いを認識して胃がんを早期に発見することが可能です。しかし、胃がんは胃炎を伴うことが多く、発見が難しい病変も存在します。
最近では、狭帯域光観察(NBI)といって特殊なフィルターにより2つの短い波長の光を胃の表面の粘膜にあてることで、粘膜の細かい表面模様や微小血管を明瞭に映すことができるようになっています。通常内視鏡では病変は認識しにくいですが(図1(左))、手元のボタン一つで病変の認識が容易になります(図1(右))。
また、拡大内視鏡(図2)は手元のレバーを調整することで85倍まで拡大できる内視鏡です。拡大された表面模様や微小血管の形態が崩れていれば“がん”と診断でき、NBIと併用することでさらに明瞭に見えます。図3(左)のわずかに陥凹した病変は通常内視鏡では“がん”と診断することは困難ですが、NBIを併用した拡大観察(図3(右))では陥凹内に茶色の崩れた微小血管を認め、生検しなくても“がん”と診断することが可能です。
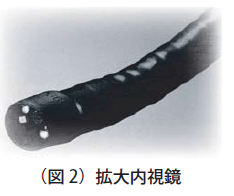

胃がんの内視鏡診断・治療は日々進歩しております。胃がんが見つかっても早期の段階であれば、より負担の少ない内視鏡での治療が可能です。早期発見、早期治療のためには定期的に上部消化管内視鏡検査を受けられることをおすすめします。ご不明な点は、消化器内科専門医までお気軽にご相談ください。

 印刷用のページを表示
印刷用のページを表示
