専門性を生かしつつ高度なチーム医療を
腎臓・血液浄化
診療方針・特色
腎臓グループは、腎炎・ネフローゼ症候群・腎不全など腎疾患全般に対する治療と、透析療法をはじめとする各種血液浄化療法を行っています。腎炎・ネフローゼ症候群に対しては、積極的に腎生検にて組織診断を行い、エビデンスに基づく治療法を選択しています。腎生検件数も年間約40~80例に達しています。IgA腎症に対する扁桃摘出・ステロイドパルス療法、多発性嚢胞腎に対するトルバプタン導入も豊富な症例経験を有しています。
地域の開業の先生方からの慢性腎臓病症例のご紹介も多く、当科にて二次性腎疾患の検索・エコーでの腎の形態評価などを行い、腎生検の要否や薬剤(SGLT2阻害薬など)追加といった今後の治療方針を決定します。その後は病状と患者さんの希望をふまえたうえで、当院と紹介元クリニックの併診の形で診療にあたらせていただきます。その際にはこまめな診療情報提供を行い、円滑かつ安全に併診ができるよう努力しております。
また新型コロナの感染蔓延の影響で開催できなかった腎臓病教室を2024年度から再開いたしました。2024年度は1回のみでしたが、2025年度からはできれば年に2回開催したいと考えております。
透析療法に関しては、例年70~110人程度の新規透析導入があります。透析療法が必要となった場合には、ビデオや透析センターの見学などを通して、患者さんの納得のいく治療法の選択(血液透析/腹膜透析/腎移植)をしていただく体制をとっています。(腎移植ご希望の場合には移植施設へ紹介させていただきます。)血液透析に関しては、新規の導入と合併症の入院治療中の透析のみを行っており、外来維持透析は行っておりません。しかし透析センターでの血液透析施行回数は毎年6,200~7,800回に達しており、その4分の3は合併症で入院中の症例です。当院の性格上、透析患者の緊急入院が多く、回転の極めて速い、重症例の多い透析センターですが、安全かつ適切な血液透析を施行できるよう医師・看護師・臨床工学技士が協力して業務にあたっております。
透析療法として血液透析しか対応できない医療機関も多い中で、当院は在宅医療である腹膜透析にも積極的に取り組んでおり、2024年度は腹膜透析の導入症例数が11例に達しました。腹膜透析導入にあたっては、カテーテルを腹腔内へ挿入する必要がありますが、できるだけ低侵襲の挿入方法である経皮的腹膜透析カテーテル留置術(Percutaneous Peritoneal dialysis Access Procedure;PPAP)を採用し、またカテーテル挿入と導入の入院を分けて、入院期間の短縮を図っています。今後高齢慢性腎不全患者の増加が見込まれ、在宅医療の重要性が高まっています。当科は往診医や訪問看護ステーションと連携して、高齢慢性腎不全患者の在宅腹膜透析にも取り組んでおり、患者さんのライフスタイルに合わせた腎代替療法の提供ができる体制を整えています。腹膜透析症例の増加に伴い、腹膜透析外来・腹膜透析指導も年間500回近くに達しています。
当院透析センターでの血液浄化療法は透析だけではありません。院内各科からの要望に応じ、単純血漿交換・二重膜濾過血漿交換・LDLアフェレーシス・レオカーナ・血液吸着・腹水濃縮・末梢血幹細胞移植など、多彩な治療に対応できる体制をとっています。 また当グループは当院の集中治療血液浄化部門も兼ねており、ICUやCCUでの最重症患者の急性血液浄化症例もきわめて多数担当しております。このため最重症患者の出張血液透析(464回)・持続血液濾過透析(CHDF)(882回)・エンドトキシン吸着(46回)などの急性血液浄化の経験も豊富です。
血液透析用シャント手術・シャントPTA・シャントエコーなどのシャント関連の手術が多いことも当科の大きい特色です。メンバーの交代もありましたが、シャント関連の手術とシャントPTA合わせると年間約1,000件という腎臓内科としては例外的に高い業績をほぼ変わらず継続しております。
診療実績
| 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
|
| 腎生検症例数 | 52 | 58 | 40 | 42 |
| 血液透析施行総数(透析室) | 7,611 | 7,255 | 6,239 | 6,818 |
| 血液透析導入患者数* | 85 | 78 | 83 | 63 |
| 腹膜透析導入患者数* | 7 | 6 | 7 | 11 |
| 腹膜透析外来・腹膜透析指導(延べ回数) | 325 | 340 | 371 | 486 |
| 透析室看護師による腎不全患者教育(延べ回数) | 88 | 103 | 151 | 131 |
| 腎臓病教室延べ参加人数(年2回) | 開催 できず |
開催 できず |
開催 できず |
1回開催 50名限定 |
| 出張血液透析施行回数(ICU、CCU、HCU) | 431 | 494 | 391 | 464 |
| 持続血液濾過透析(CHDF)施行回数 | 770 | 887 | 947 | 882 |
| エンドトキシン吸着施行回数 | 34 | 58 | 58 | 46 |
| 単純血漿交換 | 15 | 17 | 26 | 24 |
| 二重膜濾過血漿交換 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 免疫吸着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDLアフェレーシス | 7 | 0 | 0 | 0 |
| レオカーナ | 4 | 50 | 53 | 29 |
| 顆粒球除去 | 0 | 15 | 0 | 47 |
| 腹水濃縮 | 32 | 18 | 14 | 48 |
| 血液吸着(薬物中毒) | 16 |
0 | 0 | 0 |
| 末梢血幹細胞採取 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| シャント関連手術件数 | 361 | 419 | 322 | 391 |
| シャントPTA件数 | 607 | 654 | 700 | 571 |
| シャントエコー件数(中央検査部、小林大樹技師) | 3,662 | 3,586 | 3,475 | 2,686 |
*:毎年1月1日~同年12月31日の患者数
シャント関連手術内訳
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 自己血管内シャント | 228 | 289 | 187 | 173 |
| 人工血管内シャント | 45 | 39 | 37 | 34 |
| 動脈表在化 | 9 | 9 | 5 | 13 |
| 長期留置カテーテル挿入 | 58 | 64 | 60 | 94 |
| その他 | 21 | 18 | 33 | 77 |
| 合計 |
361 | 419 | 322 | 391 |
臨床研究のテーマ
- 血液透析用内シャント作成困難例における手術法の検討
- 血液透析用内シャントの狭窄形態と開存率の関係の検討
- 血液透析用内シャント狭窄例に対する薬剤溶出性バルーンカテーテルの効果の検討
- 血液透析用内シャント狭窄例に対する薬剤溶出性ステントの効果の検討
- 血液透析用シャント作成後の生命予後に関する検討
- 腹膜透析用カテーテルの非侵襲的挿入方法の検討
- 慢性腎臓病患者における加齢性腺機能低下症(LOH症候群)の検討 など
最近の論文業績
- Suemitsu K, Shiraki T, Iida O, Oka K, Ota N, Izumi M. Ultrasound-Assessed Lesion Morphology and Drug-Coated Balloon Treatment for de novo Dysfunctional Arteriovenous Fistula in Hemodialysis Patients. J Endovasc Ther Online first, Nov 30, 2023
- 末光浩太郎 穿刺と長期管理 グラフト流出路病変に対するステントグラフトの有効性 腎と透析94巻2号 245-247, 2023
- 大田 南欧美 経皮的腹膜透析カテーテル留置術(percutaneous peritoneal dialysis access procedure; PPAP)の有効性について 腹膜透析2023 腎と透析 第95巻別冊 124-125, 2023
地域への貢献・地域医療連携
下記のような活動を行っております。腎臓病教室に関しても2024年度から再開することができました。
- 慢性腎臓病患者を対象とした腎臓病教室開催(2024年度は年1回)
- 近隣医療機関との病診連携の研究会(年数回)
- 近隣訪問看護ステーションとの腹膜透析勉強会(年数回)
- 地元医師会での慢性腎臓病管理に関する講演
- 地元薬剤師会での慢性腎臓病管理に関する講演
- 近隣透析施設患者会での講演
- 兵庫県慢性腎臓病対策・連携協議会への参加
将来計画
-
日本の慢性腎臓病の患者は推定約2000万人(成人5人に1人!)と非常に多く、地域ぐるみで良好な診療体制を構築する必要があります。このためにも病診連携の研究会の開催や患者紹介・逆紹介を推進するなど、地域の医療機関との連携をより強めていきたいと考えています。慢性腎臓病の症例をご紹介いただければ、できる限りご紹介元と併診の形で診療を継続し、ご紹介いただいた先生方のご負担の少ない診療形態をとっております。地域の開業の先生方から「慢性腎臓病の症例あったら、ひとまずは関西労災腎臓内科へ。」と言っていただける体制を作っていきたいと思います。
-
血液透析療法導入に関しては年間60~110例程度の高水準を維持し、また2015年からは腹膜透析導入症例数も増えてきました。大田医師の非侵襲的な腹膜透析カテーテル挿入術(PPAP)は全国的に高い注目を集めています。腹膜透析領域で今後全国のトップランナーとなることを目指して更に努力していきたいと考えております。腹膜透析は在宅医療であり、今後の超高齢化時代に向いた治療法と言えます。慢性腎不全患者さんのライフスタイルや希望に即した最適の腎代替療法の提供ができるよう、今後更に当科の体制を発展させていきたいと考えています。
血液
血液内科では、一般的な貧血などの血液疾患は勿論のこと、白血病・悪性リンパ腫をはじめとする造血器腫瘍や、血小板の異常、あるいは凝固因子の異常をひきおこす疾患も対象としています。特に造血器腫瘍の診療に力を入れています。造血器腫瘍の診療には専門的な知識と経験が要求されますが、治癒をめざして医療を提供することを目標とし、血液専門医である常勤医が中心となってレジデントとともに診療にあたり、急性白血病に対する強力な化学療法や悪性リンパ腫に対する自家末梢血幹細胞移植を含めた超大量化学療法から分子標的治療や標準的化学療法まで積極的に取り組んでおります。また入院の短縮やQOLも考慮し、入院から外来での化学療法へスムーズに移行できる体制も整っております。血液疾患の治療の進歩はめざましく、常に質の高い治療を取り入れて更なる治療成績の向上を目指します。
診療実績(2024年度)
| 悪性リンパ腫 | 94例 |
|---|---|
| 白血病 | 27例 |
| 多発性骨髄腫 | 22例 |
| 骨髄異形成症候群 | 20例 |
| その他 | 20例 |
| 合計 | 183例 |
糖尿病・内分泌
糖尿病・内分泌グループは、糖尿病、肥満(症)、高脂血症(脂質異常症)、高血圧症、骨粗鬆症を中心とした代謝疾患、下垂体・甲状腺・副腎疾患などの内分泌疾患を診療の対象疾患としています。 常勤医は、日本糖尿病学会研修指導医2名、医員1名、レジデント1名の計4名です。当院は日本糖尿病学会の教育認定施設であり、専門知識に基づき、より厳格な血糖管理をめざしています。 1型糖尿病に対しては、強化インスリン療法、持続血糖モニタリング(CGM)、さらにインスリンポンプ療法(CSII)など先進的な診断・治療も行っています。また、代謝疾患を考える際には内分泌疾患への深い知識も必要であることから、電解質異常や副腎偶発腫瘍などにも積極的に検査を行って診断し、脳神経外科・泌尿器科・耳鼻咽喉科・放射線科と連携しながら治療介入しています。そして、何より医師個々のレベルアップのために、積極的に学会や研究会で発表することにも力点を置いています。 対象疾患の多くが「慢性疾患」であることから、近隣の実地医の先生方や他病院との密接な連携の中で、よりよい診療体系を構築しています。糖尿病は、2010年には1千万人を越え、21世紀の国民病とも呼ばれる疾患です。「強化インスリン療法の導入」「合併症の総合評価」「治療方針(薬剤選択)の決定」などを行うことにより地域の中核病院としての役割を果たして参る所存です。
診療実績(2024年)
| 疾患構成 | 糖尿病75% 内分泌疾患25% |
|---|---|
| 糖尿病内分泌内科通院中の外来患者数 | 1,912名 |
| 糖尿病内分泌内科への入院患者数 | 127名 |
| 他診療科からの血糖コントロールおよび内分泌管理の依頼件数 | 年間1,308例 |
呼吸器
2012年3月末をもちまして、常勤医が不在となっております。現在、常勤医確保に向けて努力しております。大変ご迷惑をおかけしており申し訳ございません。
スタッフ
腎臓内科
和泉 雅章(いずみ まさあき)

| 役職 | 副院長 内科部長 腎臓内科部長 医療連携総合センター長 |
|---|---|
| 資格等 | 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医 日本腎臓学会腎臓専門医・指導医・評議員 日本透析医学会透析専門医・指導医・評議員 ICD制度協議会認定インフェクションコントロールドクター(ICD) 日本医師会認定産業医 医学博士(平成12年 大阪大学) The Best Doctors in Japan 2012-2017、2020-2021、2022-2023、2024-2025 |
大田 南欧美(おおた なおみ)
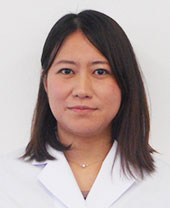
| 役職 | 腎臓内科副部長 |
|---|---|
| 資格等 | 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医 日本腎臓学会腎臓専門医 日本透析医学会透析専門医・VA血管内治療認定医 日本腹膜透析医学会連携認定医・認定医 日本救急医学会認定ICLS・BLSコースインストラクター 日本内科学会認定JMECCインストラクター |
勝間 勇介(かつま ゆうすけ)
| 役職 | 腎臓内科医員 |
|---|---|
| 資格等 | 日本内科学会認定内科医 日本腎臓学会腎臓専門医・指導医 医学博士(令和6年 大阪大学) |
坂本 早秀(さかもと さほ)
| 役職 | 腎臓内科医員 |
|---|---|
| 資格等 | 日本専門医機構認定内科専門医 日本腎臓学会腎臓専門医 緩和ケア研修会修了 |
国田 涼加(くにだ すずか)
| 役職 | 腎臓内科医員 |
|---|---|
| 資格等 | 緩和ケア研修会修了 |
| 腎臓内科レジデント |
| 谷岡 由朗(たにおか よしあき)(緩和ケア研修会修了) |
| 本多 諒子(ほんだ りょうこ) |
| 大西 由真(おおにし ゆま)(緩和ケア研修会修了) |
| 白﨑 史夏(しらさき あやか) (日本救急医学会認定ICLS・BLSコースインストラクター、緩和ケア研修会修了) |
血液内科
橋本 光司(はしもと こうじ)

| 役職 | 血液内科部長 検査科部長 |
|---|---|
| 資格等 | 日本内科学会認定内科医 日本血液学会血液専門医・指導医 日本自己血輸血学会/日本輸血・細胞治療学会認定自己血輸血責任医師 医学博士(平成11年 大阪大学) 緩和ケア研修会修了 |
糖尿病内分泌内科
山本 恒彦(やまもと つねひこ)
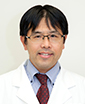
| 役職 | 糖尿病内分泌内科部長 |
|---|---|
| 資格等 | 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医 日本糖尿病学会糖尿病専門医・研修指導医・学術評議員 日本専門医機構認定内分泌代謝・糖尿病内科領域専門研修指導医 医学博士(平成17年 大阪大学) |
今田 侑(いまだ たすく)
| 役職 | 糖尿病内分泌内科医員 |
|---|---|
| 資格等 | 日本糖尿病学会糖尿病専門医・研修指導医 日本内分泌学会内分泌代謝科(内科)専門医・指導医 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医 医学博士(令和7年 大阪大学) 緩和ケア研修会修了 |
糖尿病内分泌内科医員 𠮷田 英人(よしだ ひでと)緩和ケア研修会修了
糖尿病内分泌内科レジデント 兒玉 朋之(こだま ともゆき)

 印刷用のページを表示
印刷用のページを表示
